出産したとき
出産のため退職し、夫の被扶養者となってから出産しました。出産育児一時金と家族出産育児一時金を同時に受けられるのですか? |
妻が被保険者であったため資格喪失後の出産育児一時金を請求でき、夫も家族出産育児一時金を請求できる場合、両方を請求することはできません。この場合は、いずれかひとつを選択して請求することになります。 |
妊娠3か月で流産した場合、出産育児一時金はもらえますか? |
妊娠4か月未満の場合は、出産育児一時金は支給されません。 |
双児を産んだ場合、出産手当金も出産育児一時金と同様に子どもの人数に応じて増額されますか? |
出産手当金の支給目的は、被保険者が仕事を休んだことによる収入の減少を補うことにあります。ですから、生んだ子どもの人数によって支給額が変わるということはありません。ただし双児以上を出産する場合は、産前の支給期間が98日(通常42日)まで延長されます。 |
産前産後休業中も育児休業中と同様に保険料を免除できますか? |
産前産後休業中の保険料も申請により免除できます。 |
仕事中にけがをして早産した場合、出産育児一時金はもらえますか? |
妊娠4か月以上の出産であれば支給されます。その際、けがが業務上の傷病と認められて、労災保険の給付を受けていたとしても問題はありません。 |
出産予定の医療機関が産科医療補償制度に加入しているかどうか知りたいのですが? |
医療機関等が制度に加入しているか、必ずご確認ください。医療機関等では「産科医療補償制度加入証」が提示されています。 また、産科医療補償制度ホームページ でも確認することができます。 |
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産する場合、産科医療補償制度の対象となるために手続きをすることはありますか? |
登録証は母子健康手帳に挟み込むなどして、分娩後5 年間は大切に保存しましょう。 |
「産科医療補償制度登録証」をなくしてしまったのですが? |
紛失した場合は医療機関等で再発行が可能です。医療機関等にお問い合わせください。 |
産科医療補償制度の補償対象となるのはいつの分娩からですか? |
平成21年1月1日以後に生まれた赤ちゃんから対象となります。 |
産科医療補償制度の掛金は誰が払うのですか? |
1分娩あたり16,000円の掛金は、医療機関等が支払います。 |

 シンボルマークの提示、ホームページで確認できます。
シンボルマークの提示、ホームページで確認できます。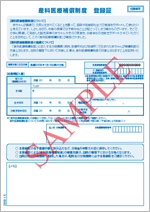 登録証に記入し、保管をお願いします。
登録証に記入し、保管をお願いします。
