HOME > 健康保険法等改正のポイント
令和7年度4月から入院したときの食事代が引き上げられます
令和7年3月までの負担額
| 一般(下記以外の人) | 1食につき490円 | |
|---|---|---|
| 下記に該当しない小児慢性特定疾病児童など 又は指定特定医療を受ける指定難病患者 |
1食につき280円 | |
| 住民税 非課税世帯 低所得者 II |
90日までの入院 | 1食につき230円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食につき180円 | |
| 低所得者 I | 1食につき110円 | |
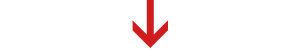
令和7年4月からの負担額
| 一般(下記以外の人) | 1食につき510円 | |
|---|---|---|
| 下記に該当しない小児慢性特定疾病児童など 又は指定特定医療を受ける指定難病患者 |
1食につき300円 | |
| 住民税 非課税世帯 低所得者 II |
90日までの入院 | 1食につき240円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食につき190円 | |
| 低所得者 I | 1食につき110円 | |
短時間労働者に対する健康保険の段階的な適用拡大について
令和4年10月1日から、従業員101人以上企業等に運用拡大。令和6年10月1日から、従業員51人以上の事業所においてパートタイムやアルバイトで働く人で、次の要件を満たす人は、原則として健康保険に加入します。
ただし、学生は除かれます。
- 週20時間以上の勤務
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
詳しくはこちら → 健康保険のしくみ > 健康保険に加入する人
